

花粉の飛散量は、日本各地で昨年より多いとの予測が出ています。
花粉症で毎年のように悩んでおられる方は、早目の対応が必要です。

 花粉症はアレルギー疾患のひとつで、スギやヒノキの花粉など、本来は身体に害を与えない物質に、 過剰な免疫反応を示します。
花粉症はアレルギー疾患のひとつで、スギやヒノキの花粉など、本来は身体に害を与えない物質に、 過剰な免疫反応を示します。
目(かゆみ、充血、涙がでる)や、鼻(くしゃみ、鼻水、鼻づまり)といった部位にでる症状のほ かに、
のどや皮膚のかゆみ、熱っぽさなどの症状が現われることもあります。
花粉症は身体が花粉に晒されることで起こるため、その年に飛散する花粉の量に発症者数は影響さ れます。
花粉の飛散量は、前年の夏の気温が高いと増える傾向があります。
2024年の夏は、気象庁が統計を取り始めて以降、2023年と並んでもっとも気温が高くなりました。
花粉飛散量の予測では、昨年と比べて、東日本はやや多いか多い。
西日本は非常に多いとなっていま す(北海道はやや少ない)。
 花粉症の患者数は増加していて、日本人の約4人にひとりとも言われています。
花粉症の患者数は増加していて、日本人の約4人にひとりとも言われています。
花粉症から身を守るには、花粉を避ける生活習慣が大切になります。
花粉の飛散情報に注意して、飛散量が多いときは不要不急の外出を控える。
外出時は、鼻をマスクで、目をゴーグルでガードする。
帰宅時は、服に付着した花粉をよく落として部屋に持ちこまないようにする、
といったことがあげ られています。
とはいえ、花粉を完全にシャットアウトすることは難しいのも事実です。
花粉症が心配な方は、治 療法を知っておくことが大事になります。
花粉症の治療には、第2世代抗ヒスタミン薬を服用する薬物療法が多く行なわれています。
粉は、例年2月中旬頃から飛散しはじめます。
花粉症の薬は、スギ花粉が飛散する2週間前(1月下旬~2月はじめ)から予防的に飲み始めるの
が効果的です。
症状が出るまえの治療は「初期療法」と呼ばれていますが、症状が出てから薬を飲んだ場合より、
症状が軽くすむというデータもあります。
 花粉症の治療法としてはほかに、舌下免疫療法があります。
花粉症の治療法としてはほかに、舌下免疫療法があります。
舌下免疫療法は、スギ花粉の抽出液を舌の裏から投与し、
アレルギー反応を弱めていく治療法です。
そのほかにも、鼻の粘膜をレーザーで変性させることでアレルギー反応が起こりにくくするレーザ
ー治療もあります。
ただ、このふたつの治療法は、花粉の飛散時期をずらして行なわれます。
花粉症に悩まれている方や症状が重くなる傾向のある方は、ご自身の症状に合った治療法や時期な
ど、
かかりつけ医に相談してください。
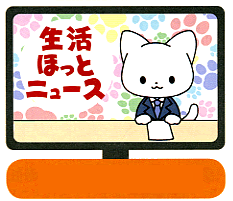 生活ほっとニュース~歩く肺炎~
生活ほっとニュース~歩く肺炎~
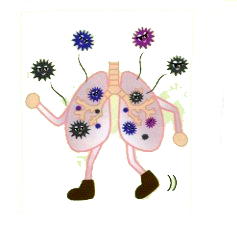
マイコプラズマ肺炎は、生物学的には細菌に分類される微生物の感染によって発症します。
この感染症は秋冬が流行期とされていましたが、今年は夏ごろから流行が始まり、かつてな いほど感染者数の増加がみられます。
マイコプラズマ肺炎の発症後は、「乾いたせき(痰の絡まないせき)」が長く続きます。
この状態を、「かぜが長引いているだけ」と判断してしまう方がいらっしゃいます。
その結果、誰かに感染させるリスクがあるまま、保育施設や幼稚園、学校、公共施設、職場
へ向かってしまう(向かわせてしまう)ケースがあります。
このように自覚がないままヒトからヒトヘと感染が広がることから、マイコプラズマ肺炎は
「歩ぐ肺炎」とも呼ばれています。
発熱、長引くせき、頭痛、のどの痛みなどが現われたのち、多くの人は症状が改善します。
ただ、まれに肺炎の重症化や、それにともなう合併症を引き起こす恐れもあります。
マイコプラズマ肺炎は、飛沫によって感染します。
せきが長引く場合は、マスクをして飛沫
の拡散を防ぎ、タオルなどの共用を避けるようにしましょう。
また長引くせきは、感染症を含めさまざまな病気のサインとなっていて、そこには重篤な病
気も含まれます。
症状が見られるときはできるだけ早めに、かかりつけ医に相談してください。
資料提供:メディカルライフ教育出版