

慢性的な痛みを抱えている人の4人にひとリが、神経障害性疼痛とされています。
神経障害性疼痛は、痛みを我慢しているうちに慢性化すると、
QOL(生活の質)の低下や精神面への悪影響が懸念されます。
 例えば、指先を切ってしまったとき、その刺激は末梢神経から中枢神経を通って脳に伝えられ、痛みとして人は感じます。
例えば、指先を切ってしまったとき、その刺激は末梢神経から中枢神経を通って脳に伝えられ、痛みとして人は感じます。
神経障害性疼痛はこうしたこととは違い、末梢神経や中枢神経が障害されることで発症します。
このため、ケガや病気によって障害された部位が治ったあとも、強い痛みが継続的に生じます。
神経が障害される原因の代表的なものには、事故やケガによる外傷性の神経の損傷、脳卒中、帯状 疱疹、三叉神経(顔の感覚を脳に伝える神経)痛、脊柱管狭窄症、糖尿病などがあげられています。
疼痛は文字だけをみると、「うずくような、ズキズキとした痛み」をイメージするかと思います。
ただ医学用語としては、「疼痛」と「あらゆる痛み」は同義語になっています。
ズキズキとした痛みのほかにもピリピリとするような灼熱痛、ビリビリと鋭く走る電撃痛、針で刺 されたような痛みなど、さまざまな現われ方をします。 痛みの強弱も一定ではなく、三叉神経痛のように「人間が感じる痛みのなかで、もっとも強い」と される症状もあります。
神経障害性疼痛には、次のような注意しなければならない特徴があります。
①神経障害性疼痛による痛みは、慢性化しやすい。また、難治性(治療が難しい状態)にな ることがある。
②神経障害性疼痛を治療しないでいると、わずかな刺激でも痛みが起こる、過敏な状態になることがある。
③痛みが慢性化、過敏化するとQOL(生活の質)の低下や精神面への悪影響が生じる。
あるアンケート調査では、「日本人は痛みを我慢する国民性」と約8割の人が回答しています。
別の調査でも、慢性の痛みを抱えている人の6割強が「痛みは我慢すべきだ」と答え、3割の人は 通院していないということがわかりました。
一時的な痛みではなく、また、早期の治療が必要な神経障害性疼痛においては、こうした考え方は 憂慮すべきものといえます。
慢性的な痛みを感じている方は我慢せずに、早目に医療機関を受診することが必要です。
経障害性疼痛は神経の障害が原因なので、痛み止めとしてよく使用される、炎症を抑えて症状を緩和するタイプの鎮痛剤は効きません。
治療には、神経伝達物質の量を減らし、働きを抑えることで鎮痛作用をもたらす薬を使用します。
また、障害された神経の周辺に麻酔を投与する「神経ブロック」や、これらの治療で痛みを抑えら れないケースでは、手術療法が検討されます。
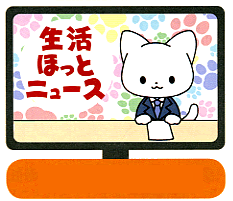 生活ほっとニュース ~りんご病~
生活ほっとニュース ~りんご病~

りんご病(伝染性紅斑)が全国的に流行しており、医療機関からの患者数の報告は、過去10年でもっとも多くなっています。
りんご病は、ヒトパルボウイルスB19というウイルスによる感染症です。
感染後、一週間程度の潜伏期間を経て、かぜのような症状からはじまり、左右の頬に赤い湿疹が生じます。
この状態がりんごを想起させるため、りんご病と呼ばれています。
りんご病は、5~9歳ぐらいの子どもに多く見られます。
この病気が重症化するケースはごくまれで、ほとんどが1~2週間程度で自然に治ります。
またりんご病は、一度感染すると終生免疫を得るため、基本的に2回目以降では症状は起こりません。
日本ではおよそ半数の人が、りんご病の免疫をもっていると考えられています。
では、りんご病流行のなにが問題となっているのでしょうか?
それは、妊娠中にりんご病に感染すると、ウイルスが胎盤から胎児に感染し、流産や死産につながるリスクが高まるためです。
また、このことが広く一般に知られていないことも問題視されています。
妊娠中の方は、かぜのような症状とともに腕や太ももに湿疹が生じたら(りんご病の特徴である頬の赤い湿疹は、成人女性の場合はあまり現われません)、軽視せずに産婦人科を受診してください。
資料提供:メディカルライフ教育出版